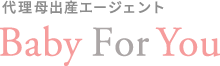2025-10-15
胚盤胞のグレードとは?妊娠率との関係・注意点を詳しく解説

体外受精や顕微授精などの不妊治療を受けるなかで、「胚盤胞のグレード」という言葉を耳にする方は多いでしょう。
胚盤胞のグレードは妊娠率を左右する重要な指標であり、治療方針を決める際の判断材料にもなります。しかし、グレードの見方や評価の基準は非常に複雑で、正しい理解が欠かせません。
この記事では、胚盤胞のグレードの意味や妊娠率との関係、注意すべき点をわかりやすく解説します。
胚盤胞とは?
胚盤胞(はいばんほう)とは、受精卵が細胞分裂を繰り返して発育した段階のことを指します。
受精後およそ5〜6日目に形成され、外側の細胞(栄養外胚葉)が将来胎盤となり、内側の細胞(内部細胞塊)が赤ちゃんの体に発達していきます。不妊治療においては、この胚盤胞の状態(グレード)が妊娠の可能性を左右する重要な指標とされています。
特に体外受精では、良好な胚盤胞を選んで子宮に戻すことで、着床率を高めることが期待できます。
受精から胚盤胞になるまでのステップ
卵子と精子が受精すると、まず「受精卵」となり、約1日ごとに細胞分裂を繰り返します。
2細胞期・4細胞期・8細胞期を経て「桑実胚(そうじつはい)」と呼ばれる状態になり、さらに発育が進むと胚盤胞になります。
この段階まで成長することで、着床に適した発達状態となり、妊娠につながる可能性が高まります。発育の過程を確認することで、胚の成長力や子宮への移植タイミングを判断する材料にもなります。
受精卵が胚盤胞にならないケースもある
すべての受精卵が胚盤胞まで発育するわけではありません。
- 卵子や精子の質
- 培養環境
- 染色体の異常
といった原因によって、途中で分裂が止まってしまうこともあります。
特に女性の年齢が上がると、胚の成長に必要なエネルギーが不足したり、染色体異常のリスクが高まる傾向があります。
胚盤胞まで育たない場合でも、治療の過程で原因を分析し、体外受精や顕微授精の方法を見直すことで次のステップにつなげることが可能です。
「胚盤胞のグレード」とは

胚盤胞の「グレード」とは、胚の発育状態や質を評価するための指標です。
胚は見た目の形や細胞のまとまり方によって段階的に評価され、グレードが高いほど妊娠の可能性が高いとされています。
この評価は、胚を子宮に戻す「胚移植」のタイミングを決める重要な判断材料にもなります。医療機関によって細かな基準は異なりますが、一般的には胚の発育段階(数字)と、内細胞塊・外細胞層の質(アルファベット)を組み合わせて表されます。
胚盤胞のグレードの例
胚盤胞の発育段階は「クラス1〜6」までの6段階に分けられます。数字が大きいほど発育が進んでいることを意味します。各クラスの胚盤胞の状態は以下の通りです。
|
クラス |
名称 |
状態 |
|
1 |
初期胚盤胞 |
胞胚腔(胞胚の中の空洞)の割合が50%以下 |
|
2 |
初期胚盤胞 |
胞胚腔(胞胚の中の空洞)の割合が50%以上 |
|
3 |
完全胚盤胞 |
胞胚腔が胚全体に広がっている |
|
4 |
拡張胚盤胞 |
受精卵をおおう透明帯が薄くなる |
|
5 |
孵化中胚盤胞 |
胚が透明帯から脱出し始めている |
|
6 |
孵化後胚盤胞 |
胚が透明帯から完全に脱出している |
この数値評価に加えて、内細胞塊と外細胞層の質をA〜Cで評価する「A・B・Cグレード」も併用されます。たとえば「5AA」や「4AB」といった表記が一般的です。
これらの組み合わせにより、胚の状態をより正確に把握できます。
このような分類方法を「ガードナー(Gardner)分類」と呼びます。
「胚盤胞移植」の流れ
胚盤胞移植とは、体外受精によって培養した胚を、受精から5〜6日後の「胚盤胞」まで育てたうえで子宮に戻す方法です。移植までの流れは、おおまかに次のステップで進みます。
- 排卵誘発剤などを使って複数の卵子を採取
- 採卵した卵子に精子を受精させる
- 培養器の中で受精卵を育成する
- 良好な状態まで発育した胚盤胞を選定する
選定された胚盤胞は新鮮胚としてすぐに移植するか、凍結して後日移植する方法があります。
胚盤胞移植のメリット・デメリット
胚盤胞移植のメリットとしては、胚がより成熟した段階で移植されるため、着床の可能性が高い点が挙げられます。また、胚の発育が確認されたものだけを選べるため、効率的な治療が可能です。さらに、子宮の環境を整えてから移植を行う「凍結胚移植」によって、より安定した結果が期待できます。
一方でデメリットとしては、すべての受精卵が胚盤胞まで育つわけではないため、培養の途中で中止となる可能性があること、また培養期間が長く費用が高くなる傾向があることが挙げられます。
胚盤胞のグレードに関する注意点
胚盤胞のグレードは妊娠率を判断するうえで参考になる指標ですが、それだけで結果を決めるものではありません。
評価の数字やアルファベットに一喜一憂するのではなく、医学的な背景を正しく理解することが大切です。ここでは、胚盤胞のグレードに関して誤解されやすいポイントを整理します。
- グレードが低い=健康な赤ちゃんが生まれないというわけではない
- インターネット上の「妊娠率」の情報に要注意
- 胚盤胞のグレードで染色体異常の判断はできない
- 胚盤胞のグレードが不妊の原因とは限らない
一つずつ、詳しくみていきましょう。
グレードが低い=健康な赤ちゃんが生まれないというわけではない
グレードはあくまで「移植時点での見た目の状態」を評価するもので、赤ちゃんの健康状態を示すものではありません。低グレードと判断された胚でも妊娠・出産に至ったケースは多く報告されています。
逆に、グレードが高い胚であっても、必ずしも妊娠が成立するとは限りません。
そのため、グレードの良し悪しにこだわりすぎる必要はないため、注意しましょう。
インターネット上の「妊娠率」の情報に要注意
ネット上では「このグレードなら妊娠率〇%」といった情報が多く見られますが、数値をそのまま当てはめるのは危険です。
胚盤胞の妊娠率は、出産経験のある若い女性に移植する場合と、不妊治療を受けている高年齢の女性に移植する場合とで大きく異なります。年齢、ホルモン値、子宮環境などの条件によって結果は変動するため、自分の状況に合ったデータをもとに判断することが大切です。
胚盤胞のグレードで染色体異常の判断はできない
グレード評価では、胚の見た目や発育状態を確認しますが、染色体の異常までは判定できません。見た目が良好でも染色体異常を持つことがあり、その逆もあります。
染色体の状態を詳しく調べる場合は、PGT(着床前遺伝子診断)などの専門的な検査を行う必要があります。
着床前遺伝子診断については、以下の記事で詳しく紹介しています。
胚盤胞のグレードが不妊の原因とは限らない
妊娠がなかなか成立しない場合でも、その原因が胚盤胞の質だけにあるとは限りません。
着床しない・流産が続くといった場合は、子宮内膜の状態やホルモンバランス、免疫機能、血流など、複数の要因が関係しています。
治療を続けても着床しない場合は、体質や環境面の見直しを行い、総合的な原因を探ることが大切です。
日本の体外受精は成功率が低いという事実
胚盤胞がうまく育たない、グレードが低いといったことで悩みすぎる必要はありません。
そもそも、日本の体外受精(ART: Assisted Reproductive Technology)による出産率は、世界の中でも相対的に低いという指摘がされているのです。
具体的には、日本では女性の出産年齢が上がっており、初婚・第1子出産時の年齢が近年高齢化傾向にあることが、妊孕性(妊娠を維持できる力)の低下と結び付きやすいとされています。
また、治療にかかる費用・通院・検査・移植といった負担が大きく、誰もが最適なタイミング・最良の胚移植を受けられているわけではないという背景もあります。
こうした状況を踏まえると、「体外受精を受けても必ず妊娠・出産できるわけではない」という現実を理解し、治療を進めるうえでの前提として認識しておくことが重要です。そして、体外受精を何回か試みても妊娠・出産に至らないケースでは、次の選択肢として、制度や実績のある海外での代理出産という道を考慮するのも有益です。
参考:不妊治療大国、しかし成功率は最下位 日本の「妊活」 不都合な真実
海外医療機関での不妊治療によって広がる選択肢

日本では法制度の制約により、利用できる不妊治療の範囲が限られています。
しかし、海外の医療機関では生殖補助医療(ART)の選択肢がより広く整備されており、妊娠や出産を望む人々に新たな可能性を提供しています。
ここでは、海外で受けられる代表的な治療のうち「卵子・精子ドナー」と「代理出産」について紹介します。
卵子・精子ドナー
海外では、第三者から卵子や精子の提供を受ける「卵子・精子ドナー」が法的に認められている国が多くあります。
卵子ドナーは、加齢などによって卵子の質が低下した女性にとって有効な選択肢です。提供された卵子とパートナーの精子を体外で受精させ、依頼者の子宮に移植することで妊娠を目指します。一方、精子ドナー制度も整備されており、男性不妊や遺伝的疾患を回避したい場合に利用されます。
匿名での提供や遺伝情報の開示方法など、国ごとにルールが異なるため、現地の制度を確認して選択することが重要です。
卵子ドナーについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
卵子ドナーとは?利用のメリット・デメリット、代理出産という選択肢を解説
代理出産
代理出産とは、医学的な理由で妊娠・出産が難しい女性に代わり、別の女性(代理母)が妊娠・出産を行う方法です。
依頼主ご夫婦の受精卵を代理母の子宮に移植し、出産後に子どもを迎える形になります。これによって、依頼主ご夫婦と遺伝的つながりがある我が子を授かれます。
アメリカの一部の州やジョージア、カザフスタン、ウクライナなどでは法的な枠組みが整っており、外国人夫婦でも利用が可能です。安全に進めるためには、医療機関と連携し、法律・契約・倫理面でサポートを行うエージェントを活用することが推奨されます。
代理出産は「自分の遺伝的な子どもを持ちたい」という願いを実現するための現実的な選択肢のひとつです。
代理出産の基本情報については、以下の記事で詳しく紹介しています。
代理出産とは?日本で禁止の理由や成功事例、費用までわかりやすく解説
海外で安全に代理出産を行う方法
海外で代理出産を行う場合、医療・法制度・言語・文化などの違いが大きいため、個人で全てを進めるのは現実的ではありません。安全かつ確実に手続きを進めるためには、信頼できる代理出産エージェントを活用することが不可欠です。
エージェントは、依頼主ご夫婦と現地の医療機関・代理母をつなぐ役割を担います。主なサポート内容は、代理母の選定、契約書作成、医療スケジュールの管理、翻訳や法的手続きのサポートなどです。国によって法律が異なるため、法的リスクやトラブルを回避するためにも専門家の支援は重要です。
また、エージェントによっては、弁護士が在籍しており、出産後の出生証明や法的手続きまでサポートしてくれるところもあります。
信頼性の高いエージェントを選ぶポイントとしては、実績数・料金体系の明確さ・現地医療機関との提携状況・口コミや利用者の声などを確認することが挙げられます。こうした専門サポートを活用すれば、言語の壁や手続きの複雑さを気にせず、安全に代理出産を進めることが可能です。
海外での代理出産をサポートするエージェントの選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
代理出産エージェントとは?選び方から費用・事例まで詳しく解説
実績のある代理出産エージェント「Baby For You」

海外での代理出産を安心してお任せできる仲介業者をお探しなら、ぜひ「Baby For You」にご相談ください。
Baby For Youでは、これまでに多くの日本人ご夫婦へ赤ちゃんをお届けしてきました。会社組織として海外の医療機関と信頼関係を築き、弁護士も在籍している、実績のある代理出産エージェントです。
代理出産プログラムのほか、卵子提供プログラム、精子提供プログラム、着床前診断・男女産み分けプログラムを提供しています。
Baby For Youはウクライナやジョージア、カザフスタンの医療機関と提携し、安心・安全な代理出産を行っています。
厳しい審査による健康な代理母の選定や、海外現地でのサポート、日本国籍を取得するための手続きなど、さまざまな面から依頼者さまをサポートいたします。
まとめ
胚盤胞のグレードは妊娠率や出産率に関係する大切な指標ですが、数字だけで結果を決めつけることはできません。低グレードでも妊娠・出産に至るケースはあり、年齢や子宮環境など他の要因も大きく影響します。また、日本の体外受精は世界的に見ても成功率が低い傾向にあり、妊娠に至らない場合は治療の見直しが必要です。
そんな中で、海外の医療機関では卵子・精子ドナーや代理出産など、より多様な生殖医療の選択肢が用意されています。専門エージェントの支援を受けながら、安全に夢を実現する方法を検討してみましょう。
※本記事の内容は、2025年10月時点の情報に基づいて作成しています。今後、ルールや法律の変更により内容が事実と異なる場合もありますので、ご了承ください。

CONTACTお問い合わせ・LINE・zoom面談
どのようなご質問でも、お気軽にお送りくださいませ。
必ず24時間以内にはお返事をお送りしております。
このご相談が『大きな一歩』になると思います。