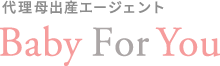2025-08-20
不妊治療をしているのに着床しない原因とは?解決策もご紹介

不妊治療を続けていても、胚移植後に着床が成立せず悩む方は少なくありません。
「反復着床不全」と呼ばれる状態は、胚や子宮の環境、免疫や生活習慣など複数の要因が絡んで起こることがあります。
本記事では、着床しない原因や考えられる母体の特徴を解説するとともに、不妊治療以外の選択肢となる「代理出産」についても紹介します。
不妊治療を続けていても着床しない……とお悩みの方へ
体外受精や顕微授精を続けても、移植後に受精卵が着床せず妊娠が成立しないことに悩む方は少なくありません。治療の過程で希望と落胆を繰り返すうちに、心身ともに大きな負担を感じることもあります。
「なぜ着床しないのか」を理解するには、まず医学的に着床とはどのような現象なのかを知ることが大切です。そのうえで、繰り返し着床が成立しない場合に考えられる原因や対策を検討することが、次の一歩を踏み出す手がかりになります。
「着床」とは
着床とは、体外受精で得られた受精卵(胚)が子宮内膜にしっかり定着し、母体とつながりを持つ過程を指します。
この段階で受精卵が内膜に定着しなければ、妊娠は成立しません。妊娠に至る大きな壁ともいえる過程であり、ホルモンの分泌状態や子宮内膜の厚さ、受精卵の質などが大きく影響します。
また、一般的に良好とされる胚を移植しても数回着床に至らない場合、「反復着床不全」と診断されることがあります。
胚移植をしても着床しない、を繰り返す「反復着床不全」
「反復着床不全」とは、良好な状態の胚を3〜4回移植しても妊娠に至らない場合に用いられる医学的な用語です。原因は一つではなく、胚自体の染色体異常や、子宮内膜の環境不良、さらには血液や免疫の異常が影響することもあります。精神的なストレスや生活習慣も間接的に関わる可能性があります。
また、着床はするものの流産を繰り返してしまうケースでは、「不育症」という疾患が疑われます。不育症については、以下の記事で詳しく紹介しています。
不妊治療でなかなか着床しない|よくある原因
着床しない理由は一つではなく、子宮の環境・免疫の状態・胚の質など複数の要因が関わっています。不妊治療を行う中でよく指摘される代表的な原因は以下の通りです。
- 子宮内膜の炎症
- 子宮内膜が薄い
- 免疫学的なトラブル
- 「着床の窓」のずれ
- 胚の問題
後述しますが、着床しない原因は不明と診断されるケースも多くあります。これらの原因が全てではなく、様々な要因によるものであることは理解しておきましょう。
子宮内膜の炎症
子宮内膜に慢性的な炎症があると、胚が定着しにくくなることがあります。クラミジア感染や細菌性膣症が影響している場合もあり、抗生物質治療や抗炎症治療で改善が期待できます。
炎症があると内膜環境が不安定になり、胚を受け入れる機能が損なわれるため、検査によって早期に発見することが大切です。
子宮内膜が薄い
着床には子宮内膜が十分な厚さを持つことが必要です。子宮内膜の薄さを指摘された場合、ホルモン補充療法や血流改善のための治療で厚さを確保することがあります。
子宮内膜が薄いと栄養や酸素供給が不足し、胚が定着しにくくなるため、移植前に内膜の状態を整えることが大切です。
免疫学的なトラブル
母体の免疫が過剰に働くと、外来の細胞と誤認されて胚を排除してしまうことがあります。
NK細胞活性や自己抗体の影響が指摘されており、免疫抑制療法や投薬が行われる場合もあります。通常、妊娠時は免疫が抑制される仕組みがありますが、それがうまく機能しないと着床阻害の要因となります。
「着床の窓」のずれ
子宮内膜には胚を受け入れる「着床の窓」と呼ばれる時期があり、通常は排卵から数日後に限られています。このタイミングがずれていると、良好な胚でも着床が成立しません。
ERA(子宮内膜受容能検査)などで最適な移植日を見極めることが可能になり、治療方針に反映されることがあります。
胚の問題
胚そのものに染色体異常がある場合、着床しても育たず妊娠に至らないことがあります。特に卵子は、加齢によって異常の割合が増えることが知られており、PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)などで事前に確認できるケースもあります。
胚の質は大きな要因であり、検査結果に応じて移植方針を調整することが治療成功に直結します。
着床不全は原因不明な場合も

不妊治療において繰り返し胚移植を行っても妊娠に至らない「着床不全」。医学的な検査で子宮内膜やホルモン環境、胚の質などを調べても、明確な原因が見つからないケースが少なくありません。
これを「原因不明の着床不全」と呼び、全体の一定割合を占めるといわれています。原因が特定できないと、適切な治療法を選ぶことが難しく、夫婦にとって精神的負担も大きくなります。その場合は生活習慣の改善や免疫調整療法など幅広いアプローチを試みることもありますが、確実な解決策はまだ確立されていません。こうした現状を理解し、治療を継続するか、新たな選択肢を検討するかを冷静に判断することが大切です。
着床不全が起きやすい母体の特徴
着床不全は子宮や胚の問題だけでなく、母体の年齢や生活習慣、体型といった要因も大きく影響します。以下は、特にリスクが高まるとされる代表的な特徴です。
- 35歳以上
- 過度なアルコール摂取や喫煙の習慣がある
- 太りすぎ・痩せすぎ
もちろん個人差はありますが、一つの参考として詳しく紹介します。
35歳以上
加齢は卵子の質に直結し、染色体異常のリスクを高めます。35歳を超えると良好胚の割合が減少し、着床が成立しても流産につながるケースが増えると報告されています。
また、年齢とともに子宮内膜や血流の状態も変化し、着床環境が整いにくくなることがあります。そのため、高齢での治療では早めの検査と適切な治療方針が求められます。
過度なアルコール摂取や喫煙の習慣がある
飲酒や喫煙は卵子や精子の質を下げるだけでなく、子宮内膜の血流やホルモンバランスにも悪影響を及ぼします。特に喫煙は子宮内膜を薄くする要因のひとつとされ、着床率の低下が明確に指摘されています。
過度のアルコールも排卵機能やホルモン分泌に影響するため、治療を受ける際には生活習慣の改善が不可欠です。
太りすぎ・痩せすぎ
BMIが高すぎる、または低すぎる場合、ホルモンバランスが崩れやすくなり、着床不全のリスクが高まります。特に肥満はインスリン抵抗性や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)を悪化させ、痩せすぎは排卵障害や子宮内膜の不良につながることがあります。
適正体重を維持することで、子宮環境を整え、妊娠成立の可能性を高められるでしょう
着床不全でも我が子を諦めたくない方へ「代理出産」のご提案

不妊治療を続けても着床が成立せず、治療の限界を感じてしまう方も少なくありません。それでも「自分の遺伝子を受け継ぐ我が子を諦めたくない」と考える方にとって、代理出産は現実的な選択肢のひとつです。
代理出産によって代理母に妊娠・出産を担ってもらうことで、ご夫婦の受精卵から新しい命を授かることが可能となります。日本では法制度が整っていないため、海外での実施が中心となりますが、信頼できるエージェントを介すことで安全性を高め、法的・医療的なサポートを受けながら進められます。
日本人夫婦が代理出産を行う方法
日本人夫婦が代理出産を希望する場合、専用のエージェントを通じて海外の医療機関や代理母と契約を結ぶ流れが一般的です。
エージェントは受精卵の作成から渡航のサポート、現地での医療調整、出産後の法的手続きまで一貫して支援してくれます。現地の言語や法律に不安がある夫婦でも、専門知識を持つエージェントが間に入ることで、スムーズかつ安全に代理出産を実現できます。
国によって費用や制度は異なるため、事前に比較検討を行い、ご自身に最適なエージェントを選ぶことが大切です。
代理出産のメリット
代理出産は、不妊治療を続けても着床が成立しない方や、妊娠が医学的に難しい方にとって、大きな可能性を広げる手段です。医学的な選択肢を超え、「我が子を授かりたい」という希望を叶えられる点が最大の魅力といえるでしょう。ここでは具体的なメリットを紹介します。
遺伝的につながりがある我が子を授かれる
養子縁組と異なり、代理出産では夫婦の受精卵を用いるため、遺伝的に依頼主ご夫婦の子どもを授かることが可能です。
特に「自分の遺伝子を引き継ぐ子どもを育てたい」という強い思いを持つ夫婦にとって、代理出産は希望をつなぐ大きな選択肢になります。体外受精で作られた胚を代理母に移植することで、妊娠・出産の過程を経て我が子を迎えられるのです。
代理母との遺伝的つながりの仕組みについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
代理出産では代理母との遺伝的つながりはどうなる?安全な実施方法を紹介
母体が高齢でもリスクを回避できる
妊娠・出産には年齢が大きく影響し、高齢になるほど流産や合併症のリスクは高まります。
代理出産では代理母が妊娠・出産を担うため、依頼する母体の年齢や健康状態に関係なく、安全に出産を目指せるのが特徴です。
加齢による妊娠・出産リスクを避けつつ、夫婦の受精卵を用いて子どもを授かれることは、心身への負担を大きく軽減する利点となります。
「卵子ドナー」との組み合わせでより確実な出産も
女性が高齢で卵子の質が低下している場合でも、卵子ドナーを利用することで妊娠の可能性を高められます。代理母と卵子ドナーを組み合わせる仕組みは、世界的に広く行われており、より確実に出産へつなげられる選択肢です。
卵子はドナーによるものでも、精子によってご主人との遺伝的つながりを保つことができます。特に40歳以上で卵子の染色体異常が増えるケースでは、この方法が現実的な手段となり得ます。
卵子ドナーと代理出産の組み合わせについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
卵子ドナーとは?利用のメリット・デメリット、代理出産という選択肢を解説
安全な代理出産はエージェントにお任せ
代理出産は医療的な知識や法的な手続きを伴うため、個人で進めるには大きなリスクが伴います。そのため、経験豊富なエージェントを通じて行うことが最も安全な方法といえます。エージェントは現地の医療機関や代理母との橋渡しを担い、治療計画から出産、帰国後の手続きまでトータルでサポートしてくれます。
また、弁護士が在籍しているエージェントを活用すれば、渡航先の国の法律や制度に準じた契約を安心して結ぶことが可能になります。さらに、妊娠中の定期的な報告や現地滞在中の生活支援など、心身の負担を軽減する体制も整っています。
代理出産は人生の大きな選択だからこそ、信頼できる専門家に任せることが安全性を高める鍵となります。
海外での代理出産をサポートするエージェントの選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
代理出産エージェントとは?選び方から費用・事例まで詳しく解説
信頼できる代理出産なら「Baby For You」
海外での代理出産を安心してお任せできる仲介業者をお探しなら、ぜひ「Baby For You」にご相談ください。
Baby For Youでは、これまでに多くの日本人ご夫婦へ赤ちゃんをお届けしてきました。会社組織として海外の医療機関と信頼関係を築き、弁護士も在籍している、実績のある代理出産エージェントです。
代理出産プログラムのほか、卵子提供プログラム、精子提供プログラム、着床前診断・男女産み分けプログラムを提供しています。
Baby For Youはウクライナやジョージア、カザフスタンの医療機関と提携し、安心・安全な代理出産を行っています。
厳しい審査による健康な代理母の選定や、海外現地でのサポート、日本国籍を取得するための手続きなど、さまざまな面から依頼者さまをサポートいたします。
まとめ
不妊治療を続けても着床しない背景には、子宮内膜や胚の質、免疫の異常、生活習慣などさまざまな要因が隠れています。検査や治療を通じて改善が期待できる場合もありますが、原因不明の着床不全が続くケースもあり、夫婦にとって精神的な負担は大きなものとなります。そんなとき、「遺伝的につながりがある我が子を授かれる」という点で、代理出産は現実的な選択肢のひとつです。日本では制度が整っていないため、海外でエージェントを介して行うのが一般的です。信頼できるプロの支援を得ながら進めることで、安全に新しい命を迎える準備ができるでしょう。
海外での代理出産をお考えの方は、ぜひ「Baby For You」にご相談ください。
※本記事の内容は、2025年8月時点の情報に基づいて作成しています。今後、ルールや法律の変更により内容が事実と異なる場合もありますので、ご了承ください。

CONTACTお問い合わせ・LINE・zoom面談
どのようなご質問でも、お気軽にお送りくださいませ。
必ず24時間以内にはお返事をお送りしております。
このご相談が『大きな一歩』になると思います。